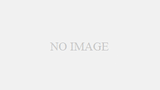節分が近づくと、「恵方巻き」に関するテレビCMがよく流れ、
多くの人が今年の恵方巻きをどこで購入するかを考え始めます。
私自身、東海地方出身で、数年前まで恵方巻き自体を知らなかった一人です。
私の地元では節分といえば豆まきが中心でした。
しかし、現在では関東地方をはじめ、
全国的に恵方巻きの知名度が高まっています。
では、関東地方で恵方巻きの習慣がいつから始まったのでしょうか?
この疑問について掘り下げてみたいと思います。
恵方巻きの関東地方での定着時期について
2015年の調査では、恵方巻きの発祥地である大阪では「今年も恵方巻きを食べる」と回答した人が50%、関東地方では約30%となっていることから、関東でも恵方巻きの普及が見て取れます。
関東地方で恵方巻きがこのように一般的になり、
知名度を高めたのは一体いつからなのでしょうか?
その歴史をたどり、恵方巻きが関東で市民権を得るまでの経緯を探ってみましょう。
のり問屋による恵方巻きの普及活動
恵方巻きの起源や発祥にはいくつかの説がありますが、
一つの説では大阪の花街で始まった文化とされています。
戦後の社会の変化でこの文化は一時的に衰退しましたが、
大阪の寿司組合が「節分には恵方巻きを食べよう」というキャンペーンを開始しました。
その後、大阪の海苔問屋組合もこの動きに加わり、
飛行機からビラをまくなどの派手な宣伝活動で普及を促進しました。
バレンタインデーにチョコレートを贈る習慣が製菓業界によって広まったように、
恵方巻きも海苔業界や寿司組合による戦略的な取り組みの一環だったようです。
恵方巻きの普及には意外と新しい歴史があります。
特に2月は寿司業界にとって閑散期とされ、
私が経験したある100円寿司チェーンでは、
年末年始の繁忙期が過ぎると客足が大幅に減少していました。
寒い季節に冷たい食べ物を避ける傾向や、
イベントの少なさもその理由でした。
そこで寿司業界と海苔業界が力を合わせて「丸かぶり寿司」の普及に努めたのですが、
当初は関東地方ではほとんど広まらない状況でした。
コンビニによる恵方巻きの全国普及
平成に入り、恵方巻きがビジネスとして捉えられるようになりました。
そのきっかけを作ったのがセブンイレブンです。
1989年、広島のセブンイレブンの社員が恵方巻きに注目し、
「節分には恵方巻きを食べると縁起がいい」というコンセプトで販売を開始しました。
最初は地域限定でしたが、初年度の売れ行きが良かったため、
販売エリアは徐々に拡大し、1995年には中国、関西、九州地方へと広がりました。
1998年には全国販売が開始され、続いて他のコンビニチェーンやスーパー、
百貨店も恵方巻き販売に乗り出し、一気に全国的な普及を見せました。
セブンイレブンが全国展開してからわずか7年で、
恵方巻きの認知率は83.6%に達し、2004年には既に全国的に知られる存在となっていました。
2010年には恵方巻きを食べる人が豆まきを行う人を上回るという結果が出ています。
コンビニ各社や小売業界の戦略が功を奏し、
新しい風習が家庭に受け入れられました。
最近では恵方ロールケーキや恵方トルティーヤなど、
さまざまなバリエーションが登場しています。
家族で一緒に楽しむなら、手作り恵方巻きもおすすめです。
簡単なレシピが動画で紹介されているので、試してみるのも良いでしょう。
恵方巻きを食べて、
ぜひ縁起を担いでみてください。