お正月の終わり1月7日に食べる七草粥。優しい味でおいしいですよね。
この時期になるとスーパー七草のセットが売られている光景を目にします。
でもどうしてこの日に七草粥を食べる風習があるのでしょう。
皆さんは七草の意味や七草粥の歴史を知っていますか。
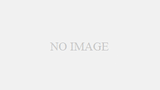
七草粥とすずなの関係
七草粥を食べる習慣は古来中国より日本へ伝わったといわれています。
七草粥を食べる理由としては「無病息災」、「長寿健康」を願う意味合いがあります。
お正月に暴飲暴食して弱った胃腸をいたわる優しい食事という意味も今では一般的ですね。
七草の種類は
・芹(せり)・薺(なずな)
・御形(ごぎょう)
・繁縷(はこべら)
・仏の座(ほとけのざ)
・菘(すずな)
・蘿蔔(すずしろ)
以上の七つです。
聞きなれない言葉ばかりですが、この七草は和歌のように五七五七七のリズムで
「せり なずな ごぎょう はこべら ほとけのざ すずな すずしろ これぞななくさ」
というように現代に伝わっています。
この中のすずなは何の葉だかわかりますか?
すずなは蕪の葉のことです。昔は蕪がとても重宝されました。
よく育ち、実の部分だけでなく葉の部分もたくさん量があり、美味しく食べられるからです。
すずなを漢字で書くと「鈴菜」とも書きます。
|
|
鈴という漢字が入っていることから縁起が良く、「神様を呼ぶ鈴」の意味もあるそうです。
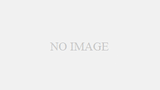
はこべらは秋ではなく春の七草です。
先ほど紹介した七草ですが、これらはすべて春の七草です。
春の七草は食用にして春の栄養を体に取りこむという意味があります。
はこべらは「ハコベ」のことでナデシコ科の二年草の野草です。
アクが少なくお浸しにして食べてもおいしいそうです。
秋には秋の七草と呼ばれる七つの草花があります。
秋の七草とは?いつ食べるのか?
では秋の七草はどんな草のことをいうのでしょうか。
女郎花(おみえなし)、尾花(おばな)、桔梗(ききょう)、撫子(なでしこ)、
藤袴(ふじばかま)、葛(くず)、萩(はぎ)、の七種類です。
この草達は食用ではなく、季節を感じるという意味合いが強いです。
「万葉集」の中で山上憶良が詠んだ歌が起源となっているようです。
春の草花は食用にし栄養を体に取り入れ、日本古来の草花を目で見て楽しむのが秋の七草です。
七草の歴史はいつからあるのか?
ここで七草の歴史についてまとめてみましょう。
七草粥を食べる1月7日は「人日の節句」といいます。
これは一年に5回ある季節の節句の一つでほかには、3月3日(上巳)、5月5日(端午)、
7月7日(七夕)、9月9日(重陽)があります。
もとは中国で唐の時代に7日の付く日に七種類の野菜を入れた汁物を食べて無病息災を祈っていました。
それが平安時代になると、日本に伝わってきたといわれています。
もともと日本でも「若菜摘み」といって雲の間から芽を出した若菜を摘むという風習がありました。
その二つが合わさって日本で七草粥が食べられるようになりました。
江戸時代になると幕府は1月7日を「人日の節句」と定め、1月7日に七草粥を食べることが民衆に広まっていきました。
こうしてみてみると、大昔からの風習が現代に残っているのですね。
七草には縁起のよい意味がこめられている
七草にはそれぞれ縁起の良い意味が込められています。
・せりは「競り勝つ」・なずなは「撫でて汚れを除く」
・ごぎょうは「仏体」
・はこべらは「繁栄がはびこる」
・ほとけのざは「仏の安座」
・すずなは「神を呼ぶ鈴」、
・すずしろは「穢れのない清白」
この意味を知っていると七草粥を食べるのも面白くなりますね。
このように七草粥には中国を起源とする長い歴史があり、日本に伝わってきました。
現代では何となく習慣でお正月の終わりに七草粥を食べるだけで本来の意味を知っている人も少ないように思います。
七草自体もすずなとすずしろ以外は手に入れることも困難なほどです。
ですがこの七草粥という日本の伝統的な風習をこれからも大切にしていきたいですね。
家族で七草の名前を覚えたり、意味を調べながら食べるとより一層楽しめるのではないでしょうか。
こちらが今売れている七草です。七草がすべて入っていて送料無料でオトクです。
まとめ
春の七草の種類や意味、七草粥の歴史は現代の日本では知らない人も多いのではないでしょうか。
日本には中国から伝わった風習や文化はたくさんありますが、七草粥の風習は日本独自に発展してきました。昔の人が大事にしてきた季節の風習をこれからも大切にしていきたいですね。
いまでは春の七草のうち、すずな(蕪の葉)とすずしろ(大根の葉)以外は簡単には手に入らなくなってしまいました。
年に一度、栄養たっぷりの七草を食べ、家族みんなで七草の意味を話しながら無病息災を願いましょう。




